一昨日から連続で書いている大切にされるインターンの性質について、当初は
・レスが早い(信頼されるインターンはボールを長く持たない)
・好奇心が前にでる(好奇心が強いインターンが仕事を任される)
・根拠をもって判断する考える
としていたのですが、3つ目の「考える」というのが、どうも広すぎる。少しひねって「根拠を持って判断する」に変更しました。インターンはどんな局面で判断をくださなければならないのか、そしてそれが何故大切なのか。
会議にて:主張するか・流れに乗るかの判断
空気を読むとは日本的な感覚で、海外では事情が違うと思われるかもしれませんが、SSHPの舞台であるシンガポールでも、いや欧米でも空気を読む状況はあります。確かにシンガポールでは、日本に比べて率直に発言することを求められますが、胸の内を探りあうような会議だってあるのです。
インターンが大きな流れに逆らうような主張をすると、どうなるでしょう?きっと場が凍りつき、糾弾や反論、場合によっては黙殺ということも考えられます。
主張が悪いとは思いません。たとえダメかもしれないけれど言わなきゃならないこともあります。ただし、インターンの多くは期限限定で、その後の関係が悪化するようなことは避けたい。
主張をするならば、リスクを承知の上で、出来る限り準備したものをぶち上げる必要があります。そして、そこに筋があると認められるようであれば、場が変わります。それはスタートアップにとっても貴重な刺激です。
タスクにて:仕事に区切りをつける判断
受験を例にして考えましょう。
5教科500点満点の試験で350点が合格ラインだとします。あなたは1教科に全時間を注いで100点を目指しますか?それとも5教科平均で70点を狙うように時間配分しますか?
この質問なら、ほぼ全員が後者と言います。
しかし仕事になると、なぜか「完璧にやらなきゃ」という気持ちが芽生えるようです。これは学力に自信がある、または完璧主義な人にその傾向が強いのですが、たいてい壁にぶちあたり、時間をロスします。
- 量がこなせない:そりゃそうですね。トータルの結果を見てみると、どんなによくてもアベレージに馴らせば20点(100/500)になるので。
- 指示が理解できていない:実はタスクの本質(求められていること)が十分理解できていなければどうでしょう・・・100点にすら届かないかもしれません。
- 模範解答が無い:タスクによっては、支持する側もアウトプットのイメージが掴みきれていないものがあります。定義されてない100点目指しても、たどり着きにくい。
「初めのタスクに手をかけ過ぎて、他にはまったく手が廻りませんでした」という状況は、お互いにとって不幸です。
仕事に区切りを付けるとは、メールを投げて、ハイ終わりというものではありません。理解→段取→作業→報告の一連の流れが完了して、ようやく区切りがつきます。
たとえ70点であっても、手順を結果を説明できれば、次のアクションに繋げることができます。仕事に区切りをつける判断ができるインターンは、指示を出すスタートアップ側の心情を汲みとっているといえます。
「決める」とは、ある意味「捨てる」ことでもあるので、とても難しいです。ですが、しっかり考えて、しっかり判断してみてください。判断が誤っていれば、それを学ぶのもインターンの仕事です。スタートアップはインターンを戦力とみなしたい一方で、力になってあげたいといつも考えています。
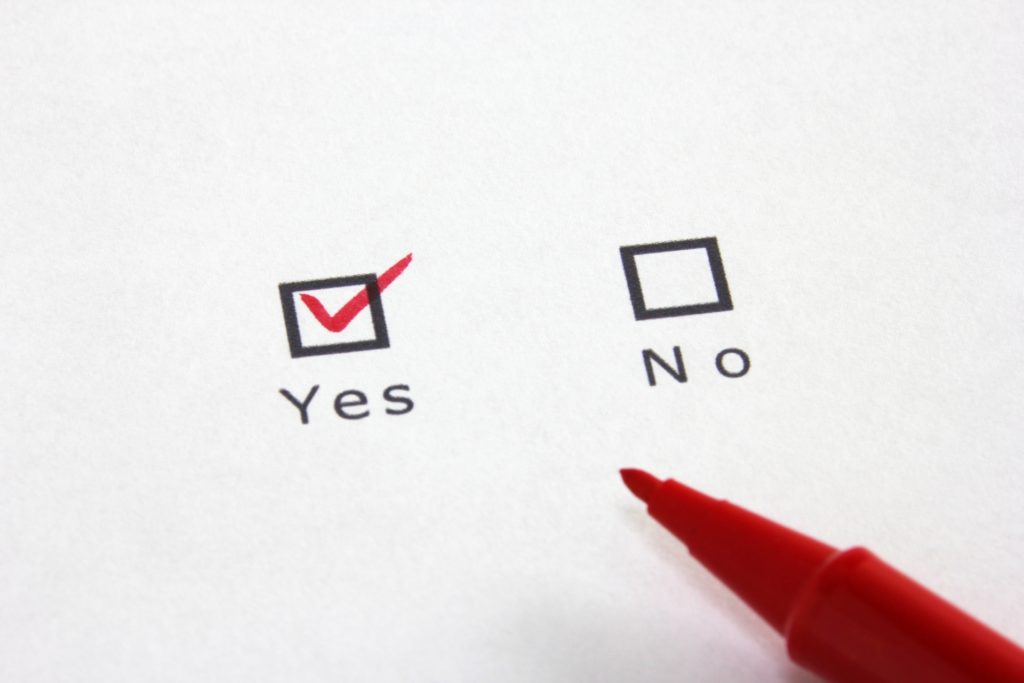






コメント